第72回日本生態学会シンポジウム 「最新のリモートセンシングで観る・測る生物圏」開催報告
中川 樹(北海道大学 陸域生態系モデリング研究室)
2025年3月15日から18日にかけて、第72回日本生態学会が開催された。札幌での開催は約8年ぶりであり、全国各地から多くの研究者が集まった。学会最終日にあたる3月18日の午前9時から12時にかけて、シンポジウム「最新のリモートセンシングで観る・測る生物圏」は開催された。デジタルバイオスフェアプロジェクトの中でもフラックス観測や生態系モデルによる研究を展開している、村岡裕由氏・加藤知道氏により、本シンポジウムは企画された。聴衆の中には多くのデジバイ関係者の姿が認められ、大盛況の下終了したシンポジウムの様子について、本稿にて議事録的に報告する。
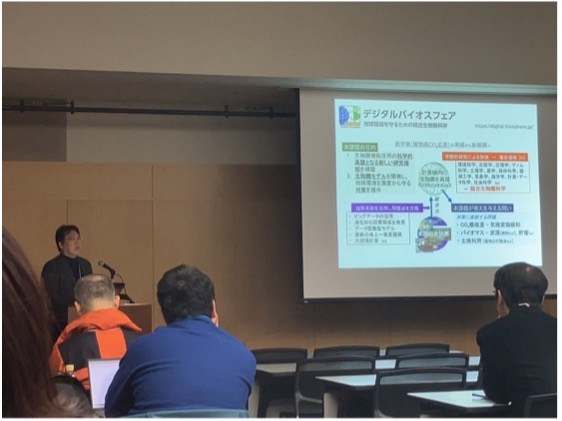
村岡氏からのシンポジウムの趣旨説明に続き、各講演者からリモートセンシングを活用した多様な研究事例が提供された。講演リストと概要は以下の通りである。
- 光化学反射指数(PRI)を用いた植生機能のリモートセンシング
彦坂幸毅(東北大学)
EVI、NDVIなどの植物量指標は長年活用されてきたが、光合成速度やストレス状態などの植生機能の定量化は困難であった。本発表では、光化学反射指数(PRI)を用いて、強光、水ストレス、温度などの環境要因に応答する植生機能を評価する手法が紹介された。実験室レベルでの計測から地球規模での植物機能推定に向けた補正法まで、PRIの実用化に向けた様々な研究例が示された。 - 地上および衛星における太陽光励起クロロフィル蛍光観測と光合成評価への歩み
両角友喜(国立環境研究所)ほか
光合成を代替的に推定する太陽光励起クロロフィル蛍光(SIF)の活用に関する発表が行われた。地上でのSIF観測による純一次生産(GPP)の推定や、放射伝達による個葉から群落レベルへのスケーリング、そしてFLiES-SIFモデルを用いた畑の群落構造や森林の垂直構造の解明など、SIFを用いた多層的な研究成果が紹介された。 - リモトーセンシングーモデル融合による森林バイオマス・枯死率・光合成の解明
加藤知道(北海道大学)ほか
日本の森林の炭素吸収量推定の精度向上を目指し、各省庁の航空機LiDARデータおよび機械学習を用いて、10mピクセル単位の森林バイオマスマッピングを行った研究が報告された。従来の森林簿や毎木調査に依存しない手法により、人の立ち入ることのできない領域におけるバイオマス評価が可能となった。この他、航空機レーダーを用いた森林成長量推定や、葉の角度分布に基づく光合成量推定の試みなども紹介された。 - ハイパースペクトル観測による北米亜寒帯林の特徴抽出の試み
小林秀樹(海洋研究開発機構)ほか
GCOM-C/SGLIセンサを活用し、アラスカの北米亜寒帯林における生物季節性を観測した研究が報告された。従来、気象条件の影響で春季・秋季のデータが不足していた同地域において、長期・連続的な分光観測を実施した。これにより、NDVIの季節変動が捉えられ、NDVIに対する林床と樹冠の寄与が季節に応じて変動すること、さらに林床植生の季節変動に対して植物種ごとに異なる寄与を示すことが明らかとなった。 - 観測ビッグデータ駆動による広域陸域炭素フラックスの高時間分解能推定
市井和仁(千葉大学)
トップダウン・ボトムアップアプローチにより、陸域生態系の炭素循環をデータ駆動型モデルで推定する研究が紹介された。ボトムアップによる炭素収支の推定では、従来のFLUXNETが欧米の観測サイトに偏っていたのに対し、本研究ではアジア独自の陸域CO2フラックスデータを作成し、評価に活用していることが報告された。また、MODIS衛星データを用いた機械学習により、純一次生産(GPP)を推定する手法も紹介された。さらに、学習データの質が推定精度に与える影響や、衛星観測とモデルとの整合性を高めるための調整の重要性についても言及された。
講演終了後には、総合討論が行われた。デジタルバイオスフィアが最終年度を迎える中、実地観測データを生態系モデルにどのように統合するかが主な議題となった。
特に、炭素循環と窒素循環の統合的理解の必要性が提起された。窒素循環に関しては、生態系モデル内での取り扱いと、実測データの比較・検証が依然として困難であることが指摘された。一酸化二窒素(N2O)やアンモニアの放出量推定、大気中の濃度分布のモデリングは進展している一方で、地上レベルでのフラックス観測や土壌状態の検証が追いついていないこと、そして、近年植物葉のC:N比が変化しているとの報告もあり、炭素と窒素の動態を一体的に把握する必要があることが改めて認識された。
また、航空機ライダーを用いた研究では、取得したデータをバイオマス量へ変換するプロセスに課題があることが指摘された。特に、広葉樹のすべての樹種に対して単一の換算式を適用しているため、バイオマス推定値には不確実性が残ってしまっている。さらに、社会実装の視点からは、企業との連携の重要性も議論された。研究成果を社会に還元し、実用化を進めていくためには、学術界と産業界の橋渡しを担う仕組みづくりが不可欠である。
本シンポジウムを通して筆者が強く感じたのは、実地観測とモデリングに関わる研究者同士が、より密接に連携してく必要があるという点である。観測者が収集するデータと、モデル開発者が必要とするデータとの間には、しばしば乖離があり、現状ではモデルにとって有用な観測が十分に意識されていない。一方で、モデルが求めるデータが観測研究として科学的意義を持つとは限らない。モデルのためだけに観測を行うのではなく、まず一次データに基づいた論文化を行い、その後にモデルや他分野で二次的、三次的に利用されるような、広がりのある研究設計が必要であると痛感した。
また、研究の社会的意義についても改めて考える機会となった。研究成果が社会に価値を還元できているかどうかという視点を欠いては、持続的な研究資金の獲得は困難となる。持続可能な研究の実現には、社会との対話や連携が不可欠であることを再認識した。

